今回は、心理の世界でよく聞く【一次感情・二次感情】について掘り下げてみました。
※ 提唱している人で一次感情・二次感情の定義が異なっていたことで、私は最初混乱しました。笑 そして、どんどん「感情」の沼にハマってしまったので、まとめておこうと思って^^
自分が感じている「感情」を適切に認識して、それを上手に扱う・表現する。これは対人関係においても、自分と仲良くなるためにも、とっても大事。
でも、クライアントさんの中には「自分の感情が分からない」という方もいます。また感情を感じられていても、「モヤモヤはするけれど……これってどういう気持ちなんだろう」と、捉えられないこともありますよね。
そんな複雑な人間の感情について、考えてみる良いきっかけになったら嬉しいです。

アダルトチルドレン(AC)克服カウンセラーのゆきです。私自身、カウンセリングを受けてからパートナーシップが劇的に改善。その後トレーニングを受けて、現在はアダルトチルドレンの生きづらさを抱える方に向けて【大切な人と良好な関係を育める】よう、講座やカウンセリングをしています。プロフィールページはこちら
※ 正しい情報を掲載するよう努めていますが、間違えることもでてくるかもしれません。ご容赦ください。
プルチックさんの感情の輪
一次感情・二次感情と調べていたら辿り着いたのが、「プルチックの感情の輪」。全部を本気で理解するのは難しいですが、感情が分からない人が自身の感情を理解するのに良さそう! 他にも……
- 感情を表現するボキャブラリーが増える
- 感情の強弱、複数の感情の組み合わさりを理解できる
ということで、進めていきます。心理学者のロバート・プルチックさんが提唱された【感情の輪】。Wikipedia
これは、8つの基本感情(一次感情)と組み合わせからなる混合感情(二次感情)で成り立っています。
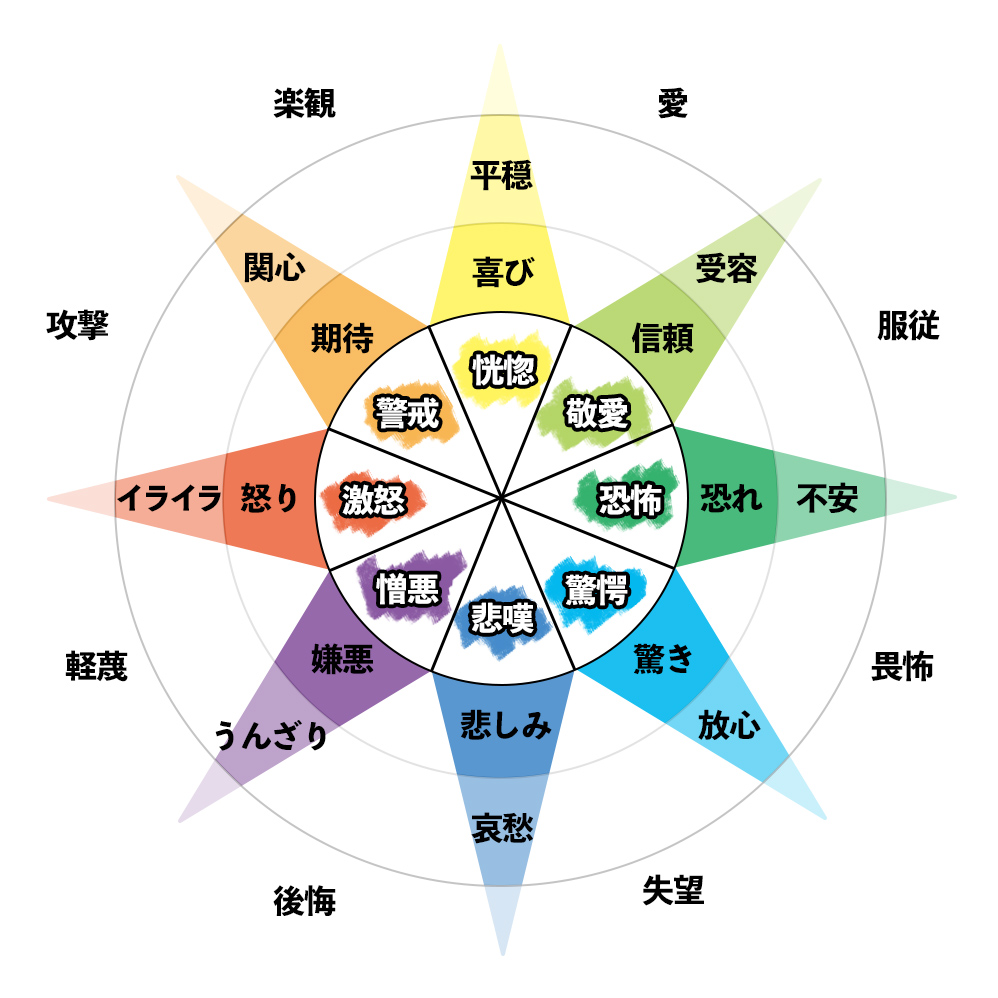
基本感情(一次感情)
プルチックさんは、主要な感情は8つと定義しました。それが8つの基本感情。2層目の部分です。
- 喜び joy(ポジティブ)
- 信頼 trust(ポジティブ)
- 恐れ fear(ネガティブ)
- 驚き surprise(中立的)
- 悲しみ sadness(ネガティブ)
- 嫌悪 disgust(ネガティブ)
- 怒り anger(ネガティブ)
- 期待 anticipation(中立的)
そしてこれ以外の感情は全て、混合状態または派生状態です。詳しくは、後術します。
感情の強弱
この図では、感情の強さも表されています。外側から中心に向かって感情が強くなります。基本感情の「信頼」が強まると「敬愛」に、逆にもう少しライトだと「容認」といった具合。
弱い段階で気づくことで、強くならないように抑えやすくなります(イライラに気づくことで激怒しない、など)。
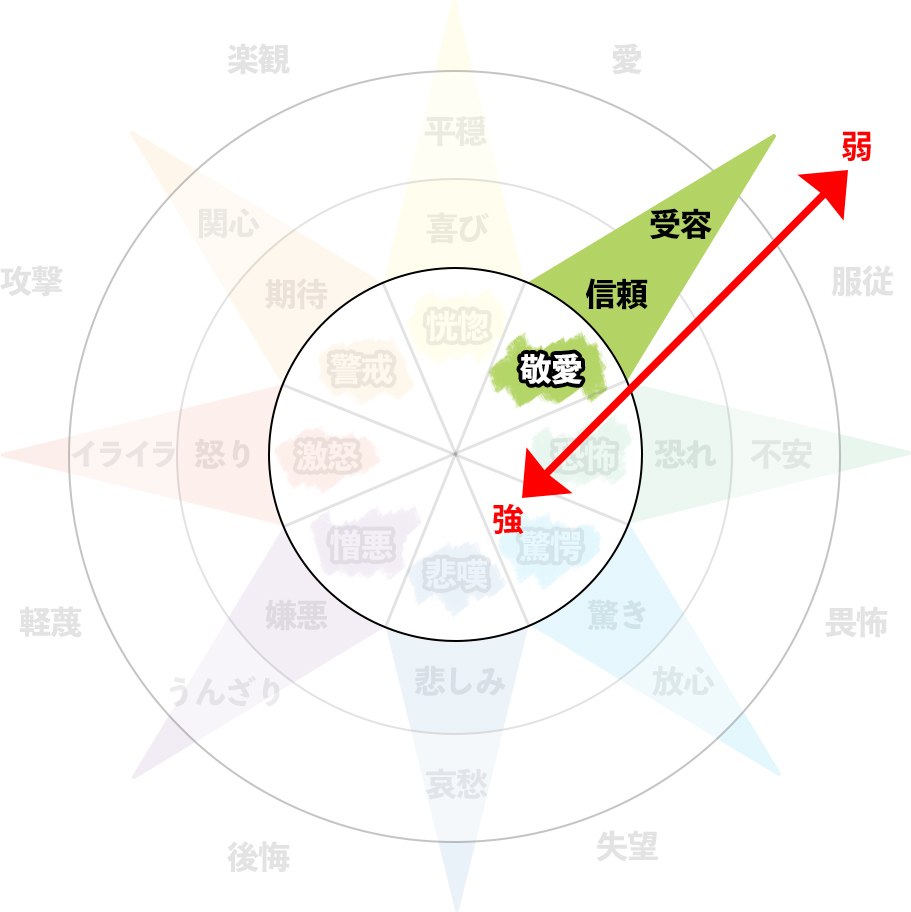
反対の感情
反対側は反対の感情を、表しています。たとえば、「嫌悪」と「信頼」は反対。
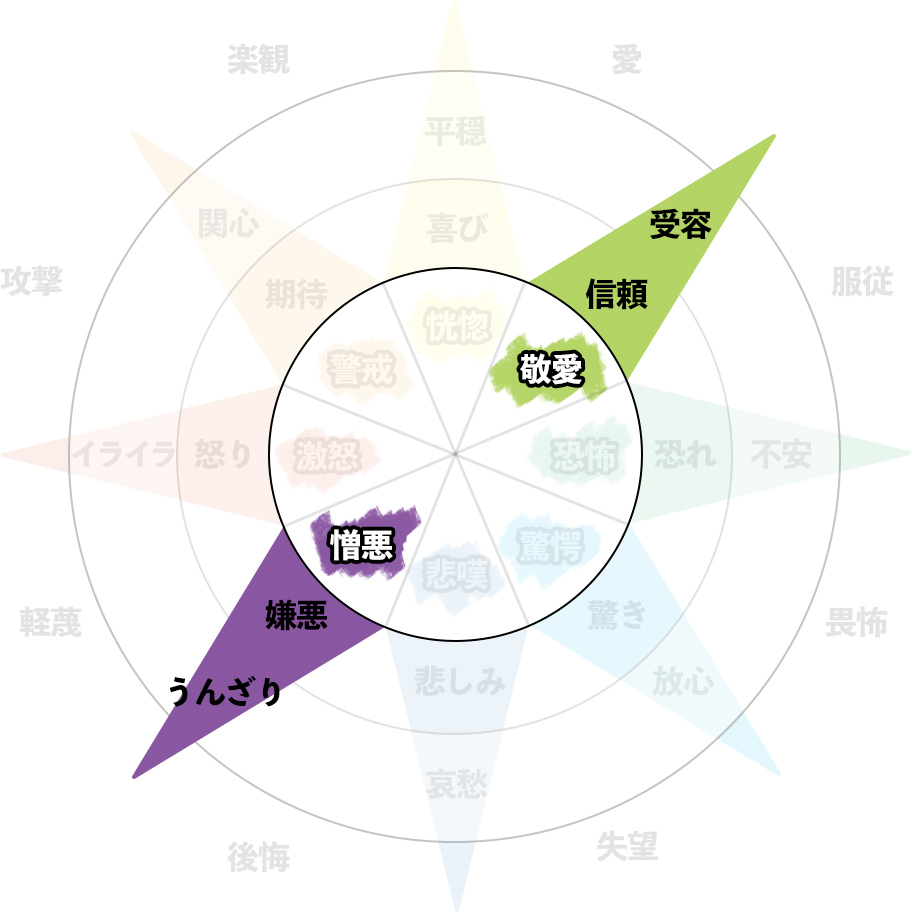
混合感情(二次感情)
複数の一次感情が混合して生じる感情のことを、混合感情(二次感情)と呼びます。
図で言うと、色のついていないエリア。例えば「喜び + 信頼 = 愛」といった具合。
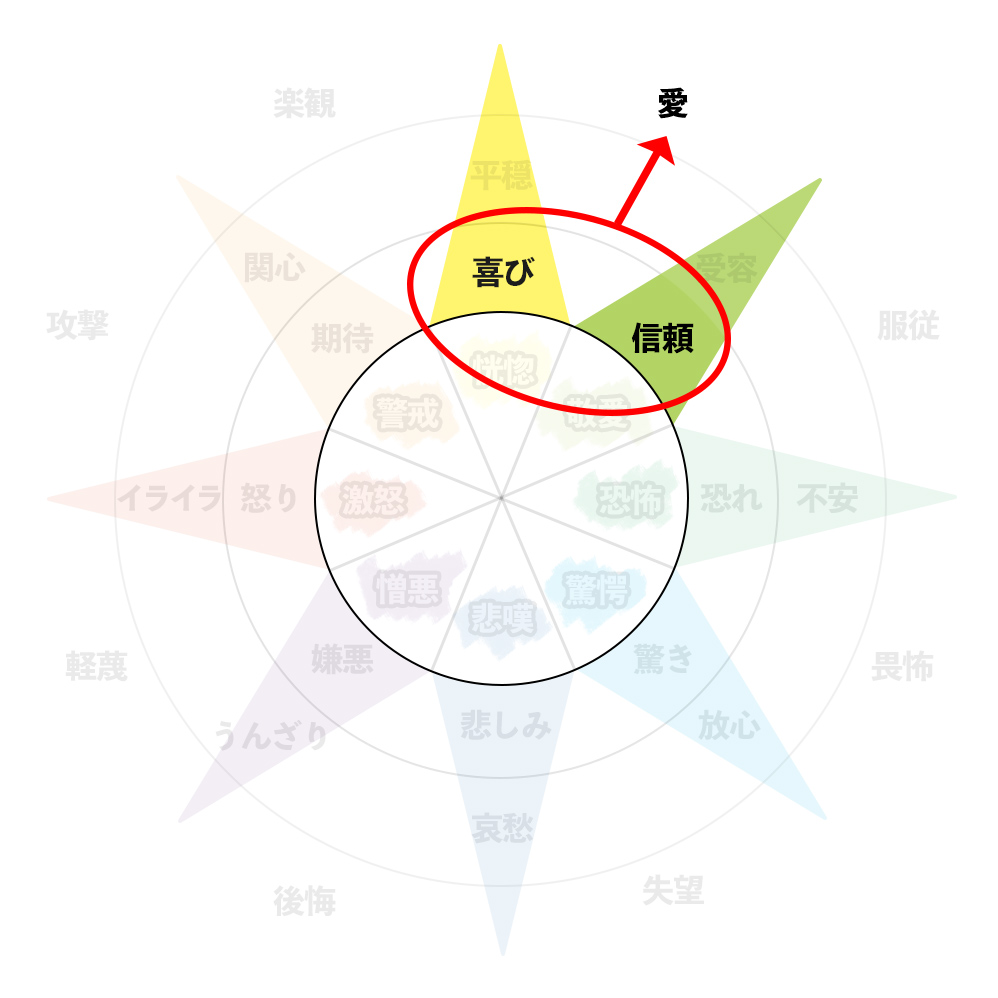
| 隣同士の混合感情 | 混合された基本感情 |
|---|---|
| 愛 love | 喜び & 信頼 |
| 服従 submission | 信頼 & 恐れ |
| 畏怖 awe | 恐れ & 驚き |
| 失望 disapproval | 驚き & 悲しみ |
| 後悔 remorse | 悲しみ & 嫌悪 |
| 軽蔑 contempt | 嫌悪 & 怒り |
| 攻撃 aggressiveness | 怒り & 期待 |
| 楽観 optimism | 期待 & 喜び |
他にも、一つ飛ばしだとこんな感じ。
| ひとつ飛ばしの混合感情 | 混合された基本感情 |
|---|---|
| 好奇心 | 信頼 & 驚き |
| 絶望 | 恐れ & 悲しみ |
| 憤慨 | 驚き & 嫌悪 |
| 悲憤 | 悲しみ & 怒り |
| 皮肉 | 嫌悪 & 期待 |
| 自尊心 | 怒り & 喜び |
| 運命 | 期待 & 信頼 |
| 罪悪感 | 喜び & 恐れ |
最後に、二つ飛ばしだとこんな感じ。
| ひとつ飛ばしの混合感情 | 混合された基本感情 |
|---|---|
| 感動 | 喜び & 驚き |
| 感傷 | 信頼 & 悲しみ |
| 屈辱 | 恐れ & 嫌悪 |
| 憎悪 | 驚き & 怒り |
| 悲観 | 悲しみ & 期待 |
| 不健全 | 嫌悪 & 喜び |
| 優越 | 怒り & 信頼 |
| 不安 | 期待 & 恐れ |
アドラーさんの一次感情・二次感情
心理学者アドラーさんは、「怒り」は二次感情と言っています。
怒りの奥には、別の本当の気持ちがある。だから、「怒りは二次感情で、本当の気持ちの方が一次感情」といった具合。
大抵の場合、「怒り」は強いパワーで前に出てくるので、一次感情を自覚できず「怒り」だけが感じられているよう。
ここが、プルチックさんのいう一次感情と二次感情との違いがありますね。プルチックさんの一次感情は、基本感情といい「怒り」も一次感情のひとつ。
概念が違うのに同じ言葉だったので、混乱してしまっていました。
一次感情
- 自分が本当に感じている感情
- 最初に感じる感情
- 出来事や状況に対する直接的な反応
例えば、「悲しみ」「寂しさ」「不安・心配」「困惑」「恐れ」「恥ずかしさ」「虚しさ」「苦しみ」「悔しさ」など。震えるような感覚のもの。
二次感情
- 一次感情を感じたことによって発生する感情
- 出来事をどう捉えたかなど思考に対する反応
「怒り」「攻撃心」「憎しみ」など、人を批判・否定するようなトゲトゲしたような感覚のもの。
「心配 → 怒り」の例
子供が約束の時間になっても帰宅せず、心配な気持ちになるお母さん。事故に巻き込まれたりしていないかなど不安がよぎりながらも、待っていて。子供が帰宅したら「なんで連絡しないのよ!!」と怒る。
「怒り」の目的
そしてアドラーさんは、「怒りの感情を持つ」のは4つの目的を果たそうとしているためと言います。
- 支配 – 相手をコントロールしようという気持ち
- 主導権争いで優位に立つ – 主導権を握りたいという気持ち
- 利権擁護 – 立場を守りたいという気持ち
- 正義感の発揮 – 正しい(と思っている)ことを教えたい気持ち
このいずれかの気持ちを満たそう(果たそう)とすることが、怒りとして表現される。
なので、怒りがでてきたときに「私のこの怒りは、どんな目的を果たそうとしているのかな」って考えてみると、元の感情(一次感情)を見つけやすくなりますね。
本当は〜してほしかった(0次)
怒りの奥には、「こうあるはずなのに」「こうして欲しかったのに」(0次)……そうでない状況が起こってしまって、悲しい・寂しい・不安などを感じ(1次)……それを隠すように「怒り」(2次)が湧き起こる。
ということは、
- 「こうであるべきなのに」が強い人
- 「こうして欲しかった」が多い(たくさん我慢してきた)人
は、怒りが強く出てきやすい。
だから怒りが出てきたら、一次感情を探して、またその奥にある0次の「本当は……」を見つけてほしい。
この部分を感じるのは、心が痛かったり辛かったりしますが、一つずつ順番に見つけてくと「感情の波に飲み込まれて苦しい」が和らいでいきます^^
なぜなら、「本当は〜してほしかった」までたどり着いたら
- 私ってずっと我慢してきたんだなっと気がつける
- ほしかったものを与えられるように動ける
から。気がついてあげるだけでも、落ち着いてきますし、自分のパターンを知ることになるので振り回されなくなります。なにより、ほしかったものを「自分自身で自分に与えよう」というステージに立てます^^
「こうあるべき」を見つけて緩ませていくことでも、怒りが出てこなくなってきますね。

この本音(0次)の部分って、とっても可愛らしいものなんです。
愛してもらいたかった
構ってほしかった
もっと見ていてほしかった
優しくしてもらいたかった……などなど
まとめ
一次感情と二次感情について調べた結果、【プルチックさんの感情の輪】と【アドラーさんの怒りは二次感情】という話に辿り着きました。
どちらも同じ「一次感情・二次感情」という言葉が出てきますが、
- プルチックさんは一次感情のことを、主要(基本)な感情
- アドラーさんは一次感情のことを、最初に感じる直接的な本当に感じている感情
ということで、そもそも定義が異なるので
- プルチックさんでは「怒り」は、一次感情
- アドラーさんでは「怒り」は、二次感情
となります。
複雑な人間の感情を理解できる、プルチックの感情の輪
プルチックの感情の輪は
- 感情の理解に良い
- 感情を表現するボキャブラリーが増える
- 感情の強弱、複数の感情の組み合わさりを理解できる
怒りの目的に気がつき、本音に辿り着くアドラーの考え方
「感情を感じきろう」と、私はよく耳にしてきて実践もしてきました。が、ただ闇雲に感じていても苦しいだけだったような気がしています。ただ感じるだけだと(目的を理解していないと)「え……それでどうしたらいいの」ってなっちゃうかなと。
怒りがでてきたら「怒ってるんだね。なんで怒ってるのかな」。一次感情を見つけるために。
一次感情を見つけたら、「寂しいんだね。どうして寂しい? 本当はどうだったらよかった? どうしてもらいたかった?」。自分の願いを見つけるために。
怒りに振り回されずに、怒りをある意味上手に使って、自分を知っていく&自分に優しくなっていく。
そのために、アドラーさんの考えかたはすごく良いですよね!
カウンセリングでは、まさにこの流れで、クライアントさんの感情を一緒にみていっています^^
ここは1人では難しい部分ですので、感情に振り回されずに上手に扱える自分になれるよう、ぜひカウンセラーさんを頼ってくださいね!

